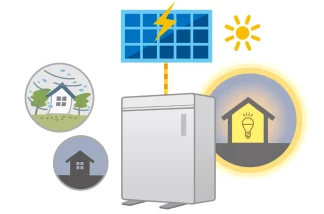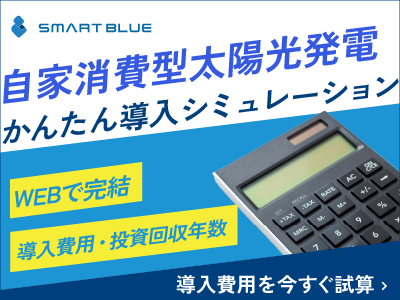【2024年3月】電気代の補助はなくなる?いつまで続くのか
電気料金 更新日: 2024.03.26
2022年から電気代の高騰が続いていましたが、2023年1月から開始された「電気・ガス価格激変緩和対策事業」により、2023年は比較的落ち着いた1年となりました。この補助は、家庭や企業の電気使用量に応じて政府がその電気代の一部を支援し負担を軽減するものです。補助制度の開始当初は、2023年9月使用分を最後に終了が予定されていましたが、補助期間の延長により2024年4月使用分までの補助が決まり、5月使用分からの補助額の縮小が決定しました。
この記事では、「電気・ガス価格激変緩和対策事業」について補助金額や延長された期間と今後の電気代の見通しについてご紹介します。
電気・ガス価格激変緩和対策事業とは
政府は、令和4年度第2次補正予算「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」として3兆円以上を計上し、エネルギー価格の高騰によって厳しい状況にある家庭や企業の負担を軽減するため、令和5年1月の使用分から、電気・ガス料金の補助を行うことを決定しました。
電気・ガス価格激変緩和対策事業は、国が値引き原資を電力・都市ガスの小売事業者などへ補助することで、家庭や企業などの利用者の請求料金を値引きし直接的に負担を軽減します。
目的
ロシアによるウクライナ侵略などの世界情勢を背景とした燃料価格高騰や、円安の影響により、エネルギー価格の高騰が続き、都市ガス代、電気代ともに値上げが続いています。電気・ガスといった光熱費の値上げは、家計や企業の業績を圧迫し、国民生活・事業活動に大きな影響を及ぼすなどの経済的な悪影響が危惧されます。
こうした状況に対する負担軽減策として、電気・ガス価格激変緩和対策事業が発表されました。特に家庭の電気使用量が増加する冬季から令和5年度前半にかけて、継続的に値下げ支援が行われます。
一部補助の対象外もある
契約プランに関わらず、ほとんどの利用者が値引きを受けることができます。
電力会社と契約していれば、法人、個人問わず低圧から高圧受電まで契約している方が使用量に応じて値引きを受けることができます。
しかし、電気代においては特別高圧の契約形態である場合、ガス代においては年間契約量が1,000万㎥以上は補助の対象外となります。
詳細は契約先の電力会社にご確認ください。
手続きは不要
電気・ガス価格激変緩和対策事業は、電力・都市ガスの小売事業者などが、国に申請を行い料金の値引きを実施するもので、電気やガスを利用する家庭や事業所では手続き等は必要ありません。
ただし、支援の対象となるのは「電気・ガス価格激変緩和対策事業」の申請手続きを行い、採択された電力・都市ガスの小売業者などです。利用している事業者が支援の採択を受けているかは、各事業者のウェブサイトや経済産業省資源エネルギー庁の電気・ガス価格激変緩和対策事業サイトなどで確認してください。
参照:経済産業省資源エネルギー庁
電気代・ガス代の値引き金額
では、家庭や企業が支払う電気代やガス代は、具体的にはどれくらい値引きされるのでしょうか。次は値引き金額の目安や確認方法について見ていきましょう。
「電気・ガス価格激変緩和対策事業」による補助金額は、電気とガスで値引き額が異なります。
2023年8月使用分(9月請求分)までは、主に家庭向けの低圧料金では1kWhあたり7円、企業向けの高圧料金では3.5円の支援が行われていました。しかし、2023年9月使用分からは補助額が半減され、家庭向けの低圧料金では、1kWあたり3.5円の支援、企業向けの高圧料金では1kWhあたり1.8円の支援となります。
以下の単価に使用量(電気の場合はkWh、都市ガスの場合は㎥)を掛けた金額が実際の値引き額です。ご家庭や企業などに届く2023年1月使用分(2月請求分)以降の請求書や検針票、web明細でもご確認ください。
| 適用期間 | 電気(低圧) | 電気(高圧) | 都市ガス |
|---|---|---|---|
| 【20023年9月終了】令和5年1月から令和5年8月 | 7.0円 | 3.5円 | 30円 |
| 令和5年9月〜令和6年4月使用分 | 3.5円 | 1.8円 | 15円 |
| 令和6年5月使用分〜 | 1.8円 | 0.9円 | 7.5円 |
値引き額については電力・都市ガスの小売業者が電気料金や都市ガス料金の算定に用いる単価のため実際の値引き額とは異なる場合があります。
補助額半減による家計には◯,◯◯◯円の影響
電気や都市ガスの値引き額は使用量に応じて変わります。
電気代の計算方法は契約形態により異なりますが、月々の電気料金は、契約容量で決まる「基本料金」使用電力量に応じて変化する「電力量料金」に、「再エネ賦課金」を加えた合計となっています。このうち電力量料金に含まれている燃料調整額に値引き単価が反映されます。
一般的な従量制の電気料金形態ではなく、定額制を利用している場合は契約種別に値引き単価が設定されています。
値引きの反映は「基本料金」ではなく、電力使用量に応じて変化する従量料金である燃料調整額に反映されます。基本料金が値引きになるわけではないため、値引き額は使用量に応じて異なります。
4人家族の月平均の電気使用量の目安は400kWh、ガス使用量は30㎥といわれています。
終了済み
この指標を基に当てはめてみると、2023年1月使用分~2023年8月使用分は電気代が2,800円・ガス代が900円の補助額となります。
2024年4月使用分まで
この指標を基に当てはめてみると、2023年9月使用分~2024年4月使用分は電気代が1,400円・ガス代が450円の補助額となります。
2024年5月使用分から
この指標を基に当てはめてみると、2024年5月使用分以降は電気代が720円・ガス代が225円の補助額となります。
2023年9月から実施されていた補助額が半減したためその分値上がりになります。
実際の値引き額については、毎月電力会社から送付される電力使用量のお知らせの検針表や請求書、契約者向けに用意されているマイページから確認することができます。
また、資源エネルギー庁の特設サイトでは、電力使用量を入力することで値引き金額を確認することができます。
資源エネルギー庁:引き続き、電気・都市ガス料金の負担軽減を行います
電気代・ガス代の補助延長の今後の見通し
「電気・ガス価格激変緩和対策による措置」は2023年1月から始まり、補助額の縮小を繰り返しながら延長を続けてきました。2024年5月使用分からはさらに補助額を縮小されることが決定しており、縮小後の補助期間については未だ明記されていませんが、前回・前々回の期間を鑑みると半年前後が予想されます。再度延長の可能性もありますが、補助額は徐々に縮小されていき終了に向かっていくと考えられます。
2024年の大手電力会社電気料金の見通し
2024年4月以降の家庭向け電気料金は、大手10社のうち6社で値上がりが決定しています。電気料金の変動は火力発電の燃料となる原油の価格が下落した点が大きな要因として挙げられます。また、一部の発電事業者において電力を送る送配電網の利用料「託送料金」が導入されこの影響も反映されます。
| 変動幅(円/kWh) | |
| 北海道電力 | -2円 |
| 東北電力 | -52円 |
| 東京電力 | 16円 |
| 中部電力 | 93円 |
| 北陸電力 | -50円 |
| 関西電力 | 65円 |
| 中国電力 | -53円 |
| 四国電力 | -62円 |
| 九州電力 | 20円 |
| 沖縄電力 | -46円 |
電気代の主な変動要素
電気代は落ち着きはじめましたが、今後の動向はまだまだ掴みづらい状況にあります。電気代はさまざまな影響を受けて変動します。ここでは、電気代の変動要素の燃料価格と再エネ賦課金についてご紹介します。
LNG・原油・石炭の供給価格による影響
日本の電力構成は火力発電が大部分を占めています。そのため、火力発電で必要になるLNGや原油、石炭などの価格が上がれば必然的に火力発電の発電コストも高くなり、それが電気代にも反映されます。
この燃料は海外からの輸出に頼っているため、国際情勢や為替レートによって大きく変動します。
燃料価格はコロナからの復興に向けた需要の増加によって高騰を始めたことをきっかけに、ロシアのウクライナ侵攻によって高騰が加速しました。
ロシアはLNGの輸出量で世界1位、原油や石炭も世界トップ3に入るほどの資源大国です。そのロシアが経済制裁を受け、輸出が制限されたことで供給量が減少して価格が高騰する事態まで発展しました。これらの燃料価格が2022年の末頃から値下がりを始めたことで、その影響で、電気代が落ち着き始めたとも言えます。
再エネ賦課金は再度値上がりへ
再エネ賦課金は、再生可能エネルギーの固定価格買取制度(FIT制度)によって電力会社が再エネ電力を買取に要した費用を、電気代の一部として利用者が使用量に応じて負担するものです。
再エネ賦課金が導入されて以来上昇を続け、2022年には制定当初の単価から約15.7倍となる1kWhあたり3.45円になりました。しかし、2023年は1.40円の半額以下に減少しました。
2023年に半額以下を記録した再エネ賦課金でしたが、2024年度の再エネ賦課金は3.49円と以前の水準まで戻ってしまいました。再エネ賦課金は再エネ特借法で定められた算定方法に則り、経済産業省が設定しています。再エネ賦課金がどのように決定されるかについてはこちらをご覧ください。
太陽光発電で電気代削減
最後に、電気代を削減する太陽光発電についてご紹介します。電気代の削減には、節電や省エネはもちろんですが、使う電気を作ってしまえばいいのです。作ってしまえば、電力会社から買う量を減らすことができ、電気代が変動してもその変動の波をある程度抑えることができます。
自家消費型太陽光発電を設置して発電した電気を自家消費すれば、その自家消費分の電気代を節約できます。蓄電池も併設すれば、昼間に使い切れなかった電力を貯めておき、夕方以降に放電することでさらに電気代を節約できるのでおすすめです。
電気代削減に関するご相談やご質問などございましたら、30分のショートミーティングを随時開催しておりますので、ちょっとしたことでもお気軽にご相談ください。ご検討状況をヒアリングしながら、弊社でお手伝いできそうなことをお話しできればと思います。
また、企業が導入する場合には、設備費を補助する補助金と節税に使える税制優遇制度が設けられています。補助金・税制優遇をまとめた資料も、以下から無料でダウンロードいただけます。